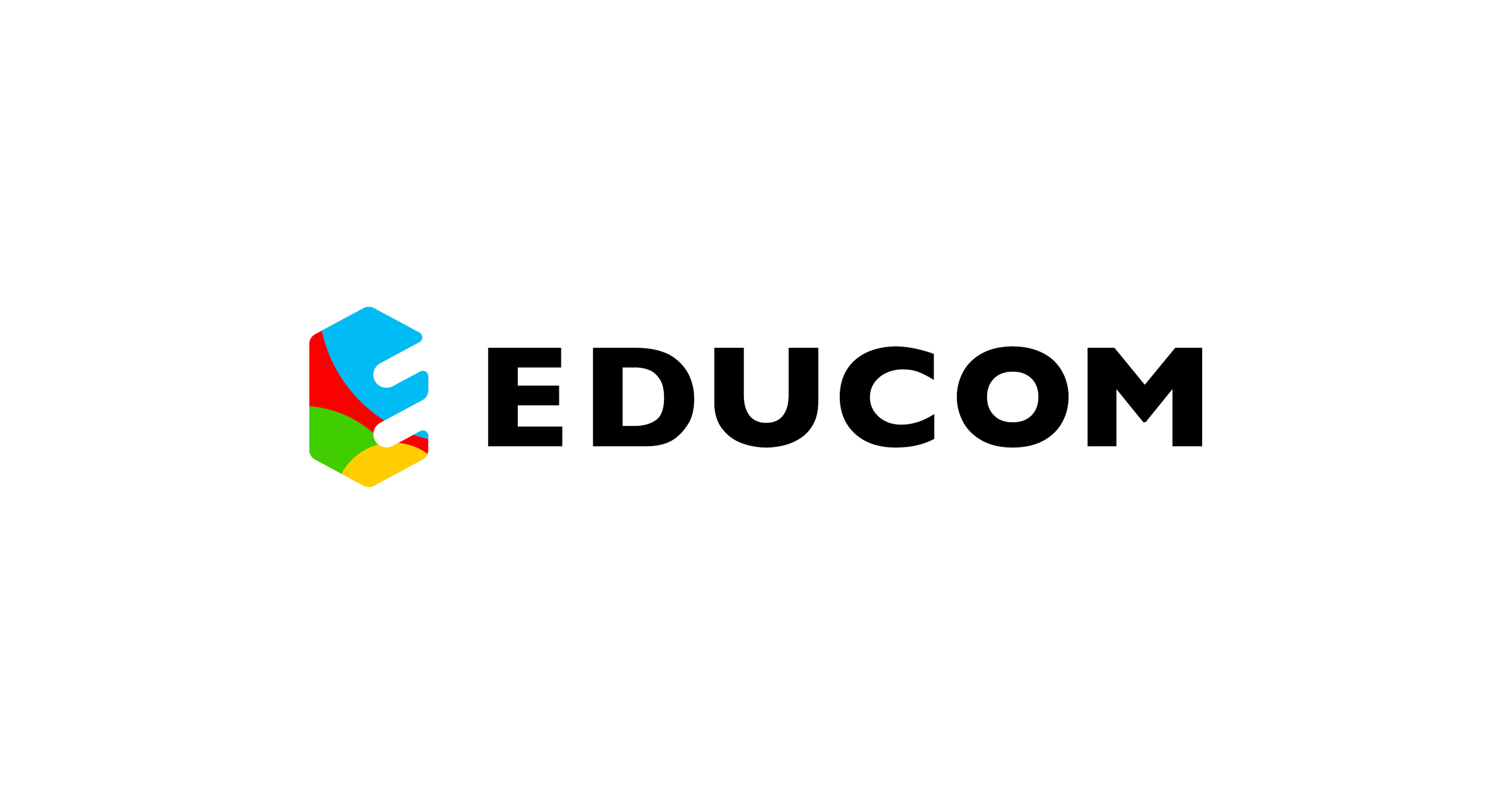「子どもの未来にワクワクをとどける」EDUCOMと臨んだ、組織に求心力をもたらす理念開発とは。
https://sweb.educom.co.jp/swas/index.php?frame=aboutus
Point
- 理念開発が権限移譲の機会となるよう、プロセスを「経営層によるミッション・ビジョンの開発」と「ミドルマネージャーから若手層に委ねるバリュー開発」と2段階に分けて設計。
- 「ずらさないこと」と「問い直していいこと」を定義した「意味のバトン」をデザイン。
- 組織構造上の適切な対話パスを設計し、権限移譲の対話を編み上げる。
「ニューノーマル」と呼ばれ始めて久しくなった、新たな生活様式への変革。この急激な変革の波は教育現場にも訪れています。株式会社EDUCOM(以下、EDUCOM)もまた、その波の中にいる企業の一つです。
創業から33年、統合型校務支援システム「EDUCOMマネージャーC4th」や、心と学びの記録・振り返り支援システム「スクールライフノート」など、学校が抱える様々な課題を解決するシステムで、教育機関におけるニューノーマルへの変革を支援し続けてきたEDUCOM。しかし、2019年に文部科学省が発表した教育改革案「GIGAスクール構想」の追い風もあり、コロナ禍において事業が急激に成長し続ける中で、組織のあり方に変化が訪れたといいます。
業績は好調であるものの、会社の急激な成長に伴い緊急の組織課題が次々に浮かび上がってくる。さらにコロナ禍により対話機会が激減し、組織への求心力が低くなってしまっている──それが、EDUCOMの抱える課題でした。
「メンバーには生き生きと仕事をしてほしいが、そうなっていないことへのジレンマがある」とは、プロジェクト開始時にある経営層のうちの一人が語った言葉です。組織が大きくなると、大胆な機会提供が生まれにくくなるのは、一般的にもよく見られること。組織の変化へ対応しながら、求心力を取り戻す。その機会づくりの一つとして、EDUCOMが取り組んだのが、MIMIGURIとの新たな理念開発でした。
事業や現場をリードしてきた自負が大きい分だけ、委ねることにも勇気が要る。
プロジェクト期間は約10ヶ月、コロナ禍により、全プロセスが完全オンラインでの実施となりました。課題である組織の求心力を高めるためには、ミドルマネージャーや若手層に”委ねる”開発を行うことは必須でした。そこで肝となるのが、権限移譲のデザインです。EDUCOMの経営層は、組織を牽引する立場であると同時に、創業期から活躍してきたプレイヤーでもあります。創業からおよそ30年。組織フェーズの変化が訪れるたびに、自らプレイヤーとしてマネージャーとして、事業や現場をリードしてきた自負があります。積み重ねてきたものが大きい分だけ、委ねることにも勇気が要る。その権限移譲の場を編むために、MIMIGURIはプロセスを「経営層によるミッション・ビジョンの開発」と「ミドルマネージャーから若手層に委ねるバリュー開発」と二段階に分けて設計しました。
開発にあたっては、理念のあり方について仮説を定義。ミッションは「10年単位で変わらないもの」ビジョンは「数年単位で戦略によって変わる可能性のあるもの」、バリューは「ビジョンに紐づいて期待されること」。特にミッションは長く使用するものだからこそ、目の前にある課題に囚われることのないように、時間軸を長期に設定。個人目線、社員目線、事業/組織目線、顧客目線など、異なる複数のポジションで視点を切り替えることにより、眼差しを自身の役職に固定しない対話を設計しました。
「そもそも、何がしたくてEDUCOMを始めたのか?」日常業務ではなかなか立ち返ることのない原点や事業への思い、人となり。それらのインタビューを経て、経営層と事業部長9名によるミッションとビジョンの開発が進んでいきます。「自立・自走する組織にしていきたい。振り返ると、自分たちもそうやって大きくなってきたように思う」。視点を切り替えながら対話を重ねるにつれて、経営層の組織への思いが浮き彫りになっていきます。
委ねるを“手放す”にしない、「意味のバトン」をデザインする。
かつて創業時に目指した頂には、もう手が届くようになった。「では、我々は次に何をやっていくのか?」──ある経営メンバーからのこの問いかけに、長い沈黙が流れます。その沈黙こそ、今まさに組織がフェーズ変化に直面していることの表れと言えるでしょう。そうして対話を重ねる中で出てきた組織への思いを構造化し、MIMIGURIはミッションとビジョンについて言葉のプロトタイプを作成。プロトタイプへの対話モチベーションを高めるために、ワークに取り入れたのが「多様決」の手法でした。
「多様決」とは、システムアーティストである安斎利洋さんが提唱している投票方法。得票数を正とする多数決ではなく、あえて賛否の意見が割れるアイデアを奨励することで、優等生的なアイデアを牽制するというものです。この多様決の採用についてMIMIGURI アートエデュケーターの臼井隆志は、「対話で合意された意味の核を確認することが目的だった」と語ります。そうしてプロトタイプに対して活発に集まる“多様”な同意や違和感をもとに、EDUCOMとMIMIGURIはプロトタイプをブラッシュアップ。ミッション「子どもの未来にワクワクをとどける」と、ビジョン「次世代学校支援システムを通して、これからの『元気な学校』の可能性を拓く」が開発されました。
続くバリューの開発では、権限移譲を明確にするため、MIMIGURIは各ステークホルダーの関与範囲の整理を実施。心配や恐れから、つい手が伸びそうになる“親心”を「あなたが関われるのはここまでです」と線引きすることが、権限移譲の肝でもあります。対話の濃度を薄めることなく安心して委ねられるよう、MIMIGURIが新たに開発したのが「意味のバトン」でした。
対話から抽出した思いとまなざしを「MUST」「WANT」「ToBE」「To THINK」と四象限で整理。「ずらさないこと」を定めると同時に「問い直していいこと」「考え、意見を挙げて欲しいこと」を選び出すことで、委ねる余地を残したバトンをデザインしました。
「もう任せようよ。大丈夫だよ」恐れを乗り越えた、“移譲”のターニングポイント。
この「意味のバトン」をどれだけ精緻にデザインしたとしても、完全に託しきるには不安が宿るのは当然のことです。そのためMIMIGURIは、バリュー開発の場を経営層がオブザーブで見学する“慣らし”のプロセスを追加。「経営層がいなくとも、濃度そのままの『意味』が行き渡っていく景色を目にするうちに、不安も少しずつ溶けていったように思う」と、MIMIGURI コンサルタントの矢口泰介は語ります。
このバリュー開発の場をいかに編むかは、これからの組織の求心力にも直結する課題です。MIMIGURIはバリュー開発において組織構造上の適切な対話パスを設計し、個々人のキャラクター性を深く見極めながら、対話の場を編み上げていきました。「次はおそらくこういう流れになるので、こんな問いを投げてみましょう」「この対話のパスは、絶対にあの方に担ってもらいましょう」──この場におけるファシリテーションの一つひとつが、これからの組織の求心力に影響する。それはさながら「試合」のような緊張感があったと、臼井は振り返ります。
このバリュー開発が進むにつれて、ある時ふと「もう任せようよ、大丈夫だよ」という言葉がEDUCOM CEO(当時)である柳瀬貴夫さんから自然とこぼれました。「もう、ハズしたものは出てこないって。信じるんだよ」──その瞬間が、理念は現場が問い直してよいものだという解釈の転換が起きた、移譲のターニングポイントとなりました。そうしてミドルマネージャーと若手層が開発したバリューは「個を大切にする」「納得いくまで対話する」「未来のために動く」「挑戦をサポートする」「時には一息つく」というもの。全社への発表は、開発者であるミドルマネージャーと若手層が自ら実施。会場のチャット欄には登壇者への応援の声はもとより、新たなバリューを歓迎する声が溢れていました。
創業以来、「元気な学校」づくりを応援し続けてきたEDUCOM。今回開発された理念が、EDUCOMという組織に人に、そして子どもの未来に、どのようなワクワクを生み出していくのか。未来につながる「何か」が生まれるのは、EDUCOMが向き合う「今日」の現場からかもしれません。
(取材・文:田口友紀子)
Project Owner
矢口 泰介
Project Manager & Planner
田中 風花
Facilitator & Planner
臼井 隆志
Project Manager
根本 紘利
Facilitator & Planner
小田 裕和
創造的な組織と事業を創りだします
共に探究する仲間を募集しています